代替可能性
労働の、あるいは言論の場における、僕という存在の代替可能性(substitutability)。これくらいの働きをして、これくらいのことを言うような人間なんて、僕以外にもたくさん、山のようにいて、だからいまこの瞬間に僕という特定不可能なひとりの男(a man)が忽然と姿を消したとしても誰も何も困らないのだ、ということ。
それは、基本的には、いいことだ。
「いつ消えてもかまわない」という事実はこのことについて考える僕をたいてい穏やかで軽々とした気持ちにさせてくれる。けっきょくのところ僕はたんなる代替可能な部品でしかない、したがって、こんな部品でしかない僕は、いろいろなものにたいしてまるで責任を負っていない、つまり自由だ、と思えるから。
しかし一方で、たまに、えっと、調子がわるいときとかに、否応なく他人と僕との途方もなく遠い距離をあらためて意識させられてしまうという、このことがもたらすさみしさやむなしさに、打ちのめされてしまいそうになる。
僕の労働や言論はもちろん代替可能。じゃあ、このさみしさやむなしさは? このぼんやりと麻痺した悲しみは?

いつものように
ひきこもりです。一歩もうごいていない。
自分でも信じられないくらいなにもできないなあ。
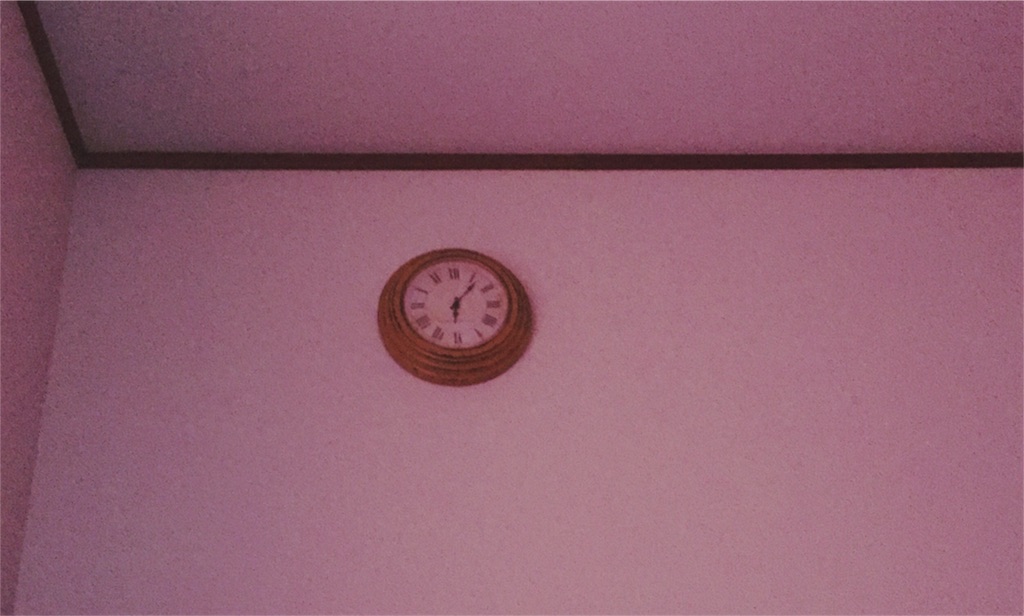
「俺」について
今日も今日とてギター片手に作曲をしていた。
「俺のTシャツは水色だから/涙を見せてもかまわない」という歌い出し。
そう、「俺」。我ながらどういう心境の変化か謎なんだけれど、さいきんなにか創作めいたことをするときの一人称が「僕」ではなく「俺」になってきている。ちなみに僕はずっと自分のことを僕って呼んでいて、俺と言ったことは人生でいちどもない。わりとめずらしいタイプだねとよく言われるし、わりとめずらしいタイプだよなあと僕自身も思う。
ところでさっき、ある人とおしゃべりをしていて、ひょんなことから「そうなの君」というキャラクター(というかなんというか)ができた。ピックに書いてくれと言われたから油性マジックできゅこきゅこ書いた。けらけら笑いながらつくったのでいろいろとやばいけど、うむ、くだらなくてたのしい時間だった。

ひきこもり
今日は一歩も外に出なかった。
部屋にこもってひとりで作曲をしていた。
こういう行動って、まったく「生産性」なんてないし、じっさい今日は明日のためにやらなきゃいけないことをぜんぜんできなかったので、やばいくらいに向こう見ずなんだけど、まあそれが自分なのかなって思う。いい曲ができたのでちょっと満足しちゃってるしさ。
「明日の朝には」という、別れの曲。
僕の歌が下手なのと、録音機材をつかうのに慣れていないせいで、誰にも聴かせることができないのがくやしい。

風の強い日
最近なかなか家の外に出ることができなかった。ベッドからでてシャワーを浴び、服を着替え、髪の毛もととのえたのに、いざドアの前に立つとなにかぼんやりとおそろしくなり、またベッドに逃げ帰ってしまうのだ。携帯の充電はずっと切れたままだったし、ストックがないのでご飯もろくにたべなかった。
かわりに、ばかみたいに眠っていた。古くて黴くさい絨毯みたいにずっしりと眠っていた。外に出てやらなきゃいけないことだってたくさんあったんだけど、なにもできなかった。
今日、ようやくドアの向こうの世界に出ることができた。ALの「さよならジージョ」をぼんやりと口ずさみながら駅までふらふらと歩いた。風がびゅーびゅー吹いていて、折られた枝が道のうえに散らばっていた。桜はとっくに緑色の葉っぱへと衣替えをしていた。天気はよかったけれど、湿度が高くて、生ぬるく、なんとなく全体的に空気が重たかった。図書館で必要な文献のコピーをして、好きな喫茶店へ行き、そこでカルボナーラを食べてコーヒーを飲んだ。おおきな本屋に行っていくつかの買い物をした。帰ってきて、携帯の電源を入れた。そしていまこれを書いている。テレビをつけることはまだできていない。

翻訳は大変
文学作品の翻訳は、任意の外国語についてはもとより、ある作家なり作品なりの語りの手法をふかく学ぶうえでも大変勉強になるため、僕にとっては一石二鳥で、ありがたく、たのしい、しかもそれはむろん文学研究の基礎でもあるので、けっして避けては通れない、というのは重々承知している、けれど、いかんせん時間が膨大にかかりがちであり、締切に追われがちであり、連日やっていると、睡眠が、死にがちである。

(創作)横浜駅にて
横浜駅の改札前を足早に歩いていると、ふいに肩を叩かれた。
反射的にふりかえったさきには、スーツ姿の知らない男のひとが立っていた。細いあごには無精ひげが薄っすらとはえていて、羽織っているダークグレーの背広はセール品らしくくたびれている。おじさんとまではいかないが、おにいさんとも呼べない、ちょうどその中間くらいの、移行期の男のひと、という感じだった。
「あの、これ、あなたのですよ」
男のひとは鈍い黄色の立方体をわたしに差し出した。古びたちゃちなブリキ缶だった。かどは泥がこびりついているみたいに赤茶く錆びついている。側面にはエメラルドグリーン色をしたポップな象がプリントされており、そのホースみたいな馬鹿げた鼻からは水がじゃばじゃばと噴出している。缶はなんとなく全体的に懐かしいような雰囲気をまとっていた。昔のドラえもんのビデオ映画とかに出てきそうだった。
とはいえ、こんなものに見覚えはない。
「ちがいます」とわたしは言って、すぐに立ち去ろうとした。急いでいた。五時からヤマハでピアノのレッスンがあったのだ。先生の長門さんはきびしいひとで、わたしがちょっとでも遅刻すると四十五分のあいだずっときげんが悪くなるのだった。
「洋子ちゃんさ、」と長門さんは憎々しげに言う。「もう来年から高校生になるんだから、遅刻なんてありえないわよ。今日はレッスン延ばさないからね、当たり前だけど」
「はい」とわたしは小さな声でこたえる。内心でうるさいオバサンだなあと毒づきながら。オバサンはべつにわたしが遅れようと不利益なんてないくせに。のほほんと楽譜をみながら待っていればいいだけじゃないか。なんでわざわざこう保護者めいたふるまいをするんだろう。
そんなふうに先週怒られて、だから今週こそはちゃんと行こうと思っていたのだが、それでもなんだかやっぱりめんどうで、ぼんやりとリビングにあるアップライトの前に座っていたら、いつの間にか目標の電車を乗り過ごしていた。気づいたときには遅かった。
余裕で間に合う、という電車から、一本後に乗り込んだ。わたしは足がはやいから、すこし走ればまだなんとか平気なはずだった。それなのに。こないだママに買ってもらった白いチュールスカートがばさりとはためいて、わたしの太ももが前に突き出た。へんなのに絡まれてしまった。もうぎりぎりかもしれないな。
「いや、君のものなんだ」
駆け出そうとしたわたしの手首を、男のひとの白くて筋ばった指がぎゅっとつかんだ。
その思いがけない強い力にわたしは動揺した。痛い。なんなの意味わかんないと思って、彼のほうを振り返った。そして、男のひとのくたびれたような顔に、ぞっとするような笑みがうかんでいるのをみた。細い目だった。たかい鼻で、薄いくちびるだった。わたしはそのすべてがひん曲がった笑みをうかべているのをみた。
わたしの脳はいっしゅん麻痺して、あたまのなかに空白がうまれた。男のひとはわたしのなかにできた空白を確認してから手を離した。逃げることを考えたけれど、ぴくりとも動かなかった。男のひとの薄いくちびるがひらいた。
「なあ、俺だよ。もう気づいたろう? 悪いな、びっくりさせたかったんだ。これまでずっと会いたかったんだよ。さみしい思いをさせてしまった。だって君がこれを落としていったのはずいぶん前で、あれから俺たちは離ればなれだったんだから」
知らない、と思った。
わたしは男のひとの顔を呆然とみつめていた。この表情も、この声も話し方も、そしてこのブリキの缶も、なにひとつ親しんでいない。彼はまったくの他人だった。この男のひとがわたしの人生にかかわったことなどこれまでいちどもなかったはずだし、当然これからもかかわりあうことなどないはずだった。
「知らない」とわたしは言った。「わからない」
男のひとの瞳の色が沼のように暗くどろどろとした黒緑に変わった。その眼はかたく凍りついていたが同時に燃えているみたいに滾っていた。わたしは彼の手に握られた缶がへこんで音をたてるのを聞いた。
「馬鹿にしやがって」と男のひとはつぶやいた。「ずっと待っていたのに。馬鹿にしやがって」
男のひとはポケットから折りたたみ式のナイフをとりだして、刃を飛び出させると、こちらに駆け寄ってきて、逃げるわたしに背後から突進しながら、力いっぱい、太ももの裏を刺した。
内側から爆発するような痛みを感じて、わたしは崩れ落ちた。ほとんど息ができなかった。太ももから突き出している異物への強い違和感。頭がくらくらした。赤黒い血がタイルにじわじわと広がっていくのがみえた。刺された、とわたしは思った。わたしたちのまわりを流れるように歩いていた人びとはまずぴたりと停止し、ついで引き潮のように後退してわたしを避け、いまではたくさんの大きな音を発生させていた。もうどうすることもできない。痛みが全身を満たした。わたしは叫びながら痙攣した、すると太ももからあふれた血がわずかにとぷとぷと波立った。生臭いにおい。白いチュールスカートはすでにびったりと黒く染まっていた。わたしを取りかこむ人びとの数はしだいに増えていくようだった。
男のひとはいつの間にか姿を消したらしい。黄色いブリキ缶だけが置き去りにされて残っていた。わたしは倒れたままだったが、両目は男の投げ捨てたブリキ缶の底をとらえていた。鈍い金属光沢のある缶の底には、子どもっぽい震える文字で、「ようこ」とサインがしてあった。

大学院の友人
小説なり詩なり、そういう作家的な活動をしている友人と、僕は大学院に入ってはじめて出会った。
学部生のころは教育学部に在籍していたので、まわりにアート好きな友人などいなかったし、いわんや創作をや、という感じで、そういう趣味を分かちあうことの快楽を知らずにここまで来てしまった。僕は少数派で、ひとりぼっちでちまちまとやっていた。それでもあまりさみしさなどがなかったのは、そもそも僕がいままで自分を異端とする環境におおく在籍してきていたからかもしれない。
それが、この大学に去年入学して以来、いつの間にか作家的な欲望を抱いている同期におおく囲まれるようになった。うれしいかぎりである。彼らは各々に個性的で、それでいてなんだか根本的に話があう(そのような状況にいるなんて僕にとっては稀有すぎる。教育学部なんて最悪だったなといまでは思う)。
僕はとくにある青年のことがお気に入りで、彼をよくご飯(学食だけど)に誘ってみたりする。彼は小説と詩を書く。書いたもののいくつかは名のある文芸誌にも掲載されているらしい。黒ぶちの眼鏡をかけていて、だいたい無精ひげを生やしている。声のトーンは高めで、いつもていねいに言葉を選んでつかう。ていねいに言葉をつかう人が僕は大好きだ。
今日は彼に小説と詩を書くときの意識の差について話してもらった。いわく、小説はどちらかというと建築的な営みであるが、詩はむしろ破壊的な営みであるという。彼は現在もっぱら詩作に打ちこんでいるらしく、そのモードに支配されているとのことで、そのためいま仮に小説を書こうという気になったとしても、登場人物のコントロールがきかなくなり、すぐに手をつけられなくなってしまうにちがいないのだそうだ。
大学の食堂に並べられたがたがたと不安定で地味な椅子のひとつに腰かけ、あたたか〜い缶コーヒーと菓子パンを頬張りながら彼の話を聞いていると、僕が目下ちょこちょこ取りくんでいるあれこれへの意欲がふたたびわいてきて(正直なところ枯れかけていた)、負けちゃいらんねえな、と意気込んだ。
食堂から大学図書館までの道すがらさんざん寒々しい風を身体に受けたにもかかわらず、僕の心がじんわりとあたたかだったのは、院の友人との久しぶりの会話でふつふつとなにかがたぎっていたからかもしれない。



